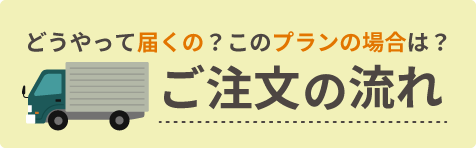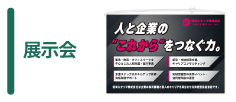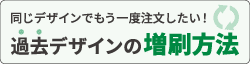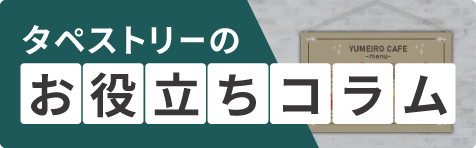着物の帯タペストリーの作り方を紹介!帯リメイクにおすすめ

着なくなった着物を再利用する方法の1つに「帯タペストリー」を作るというものがあります。タペストリーとは部屋の壁などに吊るして飾るインテリアの1つで、着物の帯を使うことで手作りでも綺麗なタペストリーを作ることができます。
この記事では着物の帯をリメイクして作るタペストリーについて、おすすめする理由と作り方の手順を紹介します。
着物の帯はタペストリーにリメイクするのがおすすめ
着物の帯をリメイクしてタペストリーを作ることで、思い入れのある着物を捨てずに新しい形で残すことができます。大切な着物からオリジナルのインテリアが作れるうえに、帯をそのまま素材として使うため材料費もあまりかかりません。
帯にはすでに柄があるため、既存の模様を活かしてインテリアや作品に仕上げることができます。和風なタペストリーだけでなく、帯のデザイン次第では洋室にも合うようなデザインにもできるでしょう。
また、手作りということもあり世界に1枚だけのタペストリーになることも魅力です。1点ものなので、プレゼントにもおすすめです。
着物の帯タペストリーを作るのに必要な物
・使わなくなった着物の帯
・裁縫道具(針や糸、はさみ、チャコペンなど)
・タペストリーの棒やその代わりになるもの(雰囲気に合わせて木の棒などもおすすめ)
・タペストリーとして吊るすための紐 (70cm~90cm程度)
・お好みでタッセルや風鎮などの飾りつけアイテム
着物の帯タペストリーの作り方の手順
1.まずは帯のどちらを上側にするか、デザインを見ながら決めましょう。上側は棒を通すため後から袋状に縫製します。仕上げたいサイズが決まったら、上側は縫い代をプラスした長さで帯をカットしましょう。縫い代の目安は8cm〜10cm程ですが、少なくとも使用する棒の直径が入る長さは必要になるので、実際に使う棒のサイズを確かめましょう。
2.帯の下側も仕上がり線から縫い代分を考慮した長さでカットします。こちら側にも棒を入れる場合は上側と同じ程度の縫い代が必要になりますが、棒を入れない場合は1.5cm程度が目安となります。今回は棒を入れない方法で作成します。
3.帯の生地が重なり合った部分を縫い合わせます。縫い方は問いませんが、厚手の生地の場合は千鳥がけ縫いなどがよいでしょう。
4.次に、帯の裏側にチャコペンで縫製する位置の印をつけていきます。上側の端から実際に帯を折り返して、想定している仕上がりのサイズになる位置に印をつけます。
5.チャコペンで付けた印にあわせて折り縫います。縫い方はまつり縫いやかがり縫いなど、お好みの方法で問題ありません。縫い目が目立ちにくい縫い方がおすすめです。
6.上側の縫製ができたら、下側も同様に折り返して印をつけ縫製していきます。この時、どのような仕上がりにするかによって加工方法も変わります。1例としてV字状にカットする方法があります。下側の端のちょうど真ん中が頂点になるようにV字に折りこみ、縫製します。
7.すべての縫製が済んだら、用意していたタッセルや風鎮などの飾りをお好みで取り付けましょう。V字に作成した場合は、V字の頂点にタッセルや風鎮を垂らすようにつけるのがおすすめです。他にも、帯の中心部分にデザインにあわせて飾りを貼り付けるなどして、より豪華に仕上げることもできます。
8.最後に紐を取り付けます。使用している棒が筒状のものであれば、紐を通した後に結ぶことで吊るすことができます。筒状ではない場合は、棒の両端に紐を結びつけるなどの方法があります。
まとめ
着物の帯タペストリーは、帯の柄や使うアイテム、切り方やサイズによって多種多様な仕上がりになります。今回ご紹介した手順をベースにしながら、お手持ちの着物の柄を活かした自分なりの作り方を見つけてみてください。
以下の記事では、着物以外の素材で手作りのタペストリーを作る方法について紹介しています。着物のタペストリーを作る時にも参考になるので、ぜひご覧ください。